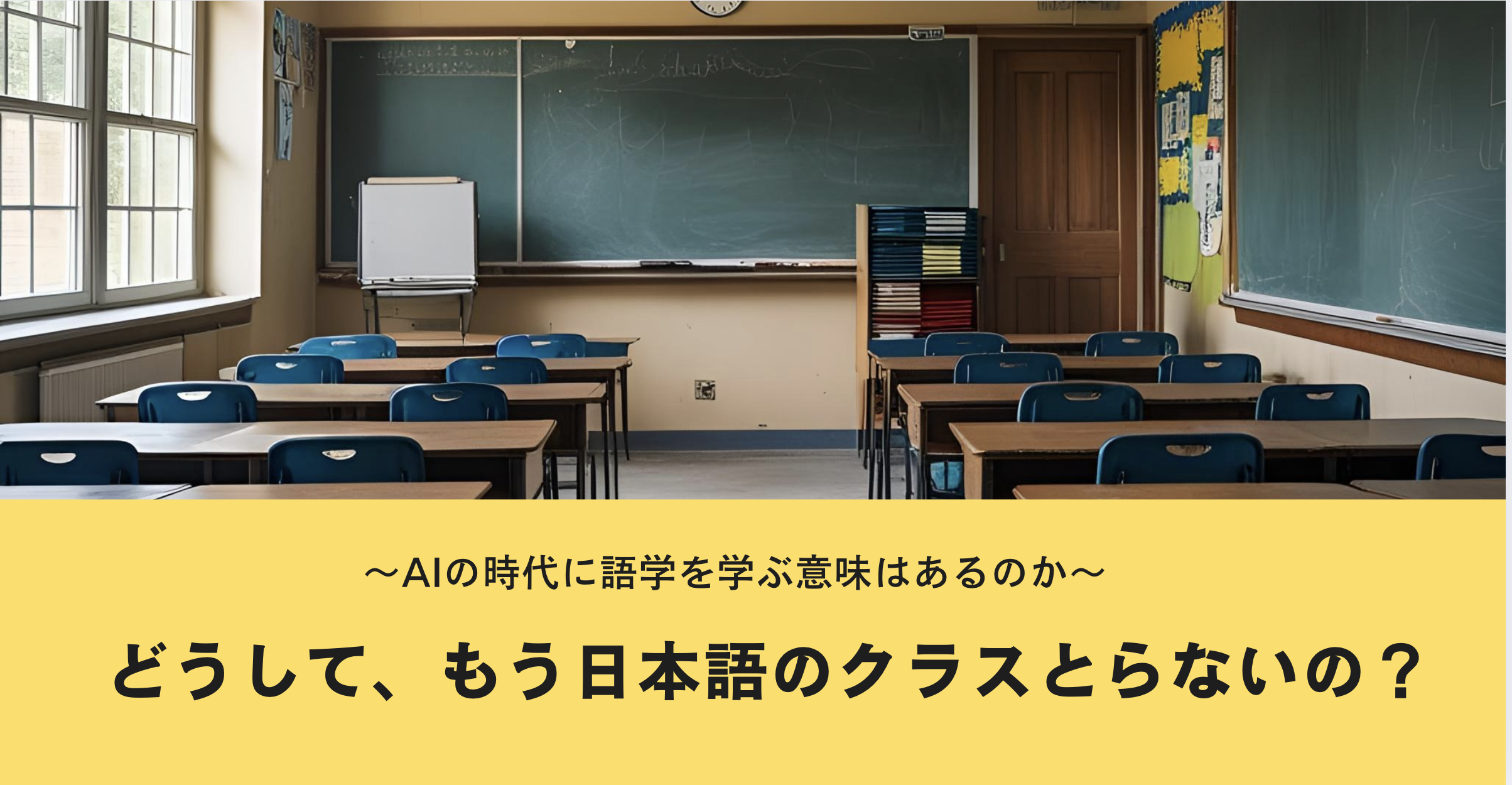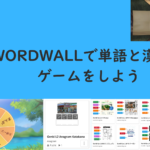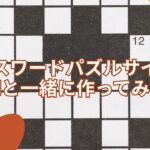AIの時代に語学を学ぶ意味はあるのか。
みなさんこんにちは。日本語教師のHinakoです。
今日は、私の心の中にずーーーとある疑問を吐き出します。
「もしかして、もう語学を学ぶ必要なんてないんじゃないか?」
ChatGPTが突然でてきて、あっという間にAIの時代になり、こんなふうに思っているのは、
私だけでしょうか。
というのも、今やAIの進化は半端なく早い。正直もうついていけない。次から次と新しいのが出てきて、もう私は学ぶことに正直疲れています。
語学教育に関して言えば、翻訳アプリを使えば、言葉の壁なんて一瞬で乗り越えられます。わざわざ単語や文法を覚えたりしなくても、AIがすぐに訳してくれる。文章を書くのも読むのも、ある程度のことはAIがカバーしてくれる時代です。
たとえば、日本旅行をする時。レストランのメニューや商品説明が読めなくても、スマホのカメラをかざせば即座に翻訳してくれます。実際そんな外国人の方、日本でたくさん見ましたし、私の外国人の友達もWi-Fiなしでも使えたから便利だったと言っていました。
現地の人と会話をするにしても、タクシー運転手さんは、外国人の方は翻訳アプリを通して会話してくると言っていました。そして外国人旅行者が増えているからでしょうか、普通に英語で対応されてるお店の日本人の方をたくさん見かけました。いや、日本人とは限らず、外国人の方がコンビニや薬局など、身近な所で働いてる姿が当たり前になったように感じます。
となると、「わざわざ大学の授業を受けて、自分で言語を勉強する意味って何なんだろう?」と、考えてしまいます。
もちろん、語学を学ぶことには文化の理解とかがあるかもですが、現実的な必要性という意味では、AIがこれだけ支えてくれるなら、学ぶモチベーションってあるのかなと。
私たちは今、「言語を学ぶ理由」そのものを改めて問い直さなければならない、新しい時代に立っているのかもしれません。そして厳しい現実。
実際、多くの教育現場では、私が知る限り、カナダですが、日本語学習の継続率の低下が深刻な課題となっていると思います。
継続率を高めるためにできること
語学教育がAIに取って代わられる時代だからこそ、人間だからこそできる学びの喜びを提供するための工夫が求められます。私が考える工夫は、やはりラポールの形成。ラポールというのはフランス語で架け橋。つまり、先生と学生さんのラポール、学生さん同士のラポール、ここを強くするのを忘れてはいけないと思います。
- 先生と学生のラポールを強くするには
フィードバックを重視!とにかくフィードバック。スモールステップからの小さい成功体験をたくさんさせ、褒めて褒めて、もちろん改善のための具体的なアドバイスもする。ちゃんと学生さんの気持ちによりそって、目をみて、伝えるしかないのでは。私はあなたをちゃんと見てますよと。怖いですが。 - 学生同士のラポールを強くするには
相互評価、ペアーワーク、グループワークを通してできるピアラーニング、多分これらはよくされていると思うのですが、「学習コミュニティの形成」これも大切だと思っています。クラスの中や外で先輩が後輩に教えるメンター制度は大事なんじゃないかと。先輩TAをクラスに入れるのもあり、クラス外でヘルプセッションを先輩たちがするのもあり。日本語のイベントをしたり、ただの雑談や勉強ができる場所を学生さんに提供するのも悪くないなと思います。それはディスコードのようなオンラインの場所でも、実際のクラスルームでも、つながる場所を提供することなんじゃないかなと。
終わりに
今の大学生は300人、400人規模の大きなクラスをとっています。特に1年生!すると隣の人と話す機会がない、つまり、誰とも話さず大学に行って帰ってくることもあるそうです。大学で友達ができない。でも日本語のクラスをとって友達ができたという話は多く耳にします。大学時代に一緒に日本語のクラスをとった子たちが今も集まって友達でいるという話も少なくないです。結婚したケースもある!これってすごくないですか。
語学教育の未来は、AIに任せるだけでなく、「人と人がつながる」をどう育てるかにかかっているのではないでしょうか。
まあ時代の流れに逆らえず、これは大学全体の問題なのかもしれないんですが、足掻けるうちは足掻きたいと思ってる次第です。
読んでいただいてありがとうございました。
参考までに、下記は「大学日本語教育における履修継続率低下の主因と有効な対策」をChatGPTにDeepリサーチしてもらった結果です。
参考までに
- 教材・授業内容の難易度/進度の問題: 授業の進度が速すぎたり、学習内容が難しすぎると感じると、学生は負担を感じて履修を継続しにくくなりますjapanese-edu.org.hk。実際、「日本語が上達するまで予想以上に多くの学習時間が必要」と感じることも継続を妨げる要因とされていますjapanese-edu.org.hk。
- 学習意欲の低下・目標の喪失: 時間の経過とともに日本語への興味を失ったり、当初の学習目標(例:日本語能力試験合格など)が消失すると、履修継続の動機づけが弱まりますjapanese-edu.org.hk。将来日本語を使う必要性を感じなくなることも一因であり、文化・言語への関心低下は学習継続意欲の減退につながりますgrowkudos.com。
- 自己効力感の低下・達成感不足: 日本語の成績不振や学習上の成功体験の欠如により、「自分は日本語学習の能力がないのでは」と自己効力感が下がると、継続意欲が大きく損なわれますjapanese-edu.org.hk。実際に「日本語の成績があまり良くなかったこと」が履修中断の理由に挙げられておりjapanese-edu.org.hk、十分な達成感が得られないことが学生の離脱につながります。
- 教員の指導法・授業スタイルの影響: 教員の教え方やクラス運営が学生の学習スタイルに合わない場合、授業への不満や興味低下を招き、履修中断の一因となりますjapanese-edu.org.hk。例えば「教師の教え方が自分に合わない」ことを理由に挙げる学生もおり、教師要因は履修継続率に影響し得る重要な要素ですjapanese-edu.org.hkjapanese-edu.org.hk。
- 他教科や時間割との競合: 専攻の必修科目や他の科目との時間割重複、あるいは学業全体やアルバイトが忙しすぎる場合、日本語科目に割ける時間がなくなり履修を続けられない学生が多くいますjapanese-edu.org.hkjapanese-edu.org.hk。実際、「専門科目の勉強を優先する」「アルバイトに忙しい」といった理由は履修継続を妨げる主要因として報告されていますjapanese-edu.org.hk。
- 文化的要因・言語不安: 異文化環境での学習によるストレスや日本語で話すことへの不安(外国語不安)、クラス内での所属感の欠如なども継続率低下に影響します。学習者の文化的・言語的背景によって動機づけや継続意思が左右されることが指摘されておりgrowkudos.comgrowkudos.com、心理的要因への支援不足(例:教室での孤立や不安の放置)は履修離脱につながりやすいと考えられますfukutake.iii.u-tokyo.ac.jp。
- 履修制度上の要因(単位・プログラム構成): 日本語科目が卒業単位に直結しない場合や、日本語専攻・副専攻制度がない場合、継続学習のインセンティブが弱くなりますcajle.ca。上級科目の未開講や開講数の少なさも指摘されており、学習者が「続けても履修できるクラスがない」「履修しても資格につながらない」と感じると継続率が下がる傾向がありますjapanese-edu.org.hkcajle.ca。
有効だと思われる対策
- 難易度・カリキュラムの最適化: 学生の習熟度に合った教材選定や無理のないペース配分を行い、過度な負担感を軽減します。授業内容が難しすぎず適切な挑戦となるよう調整することで、学生の離脱を防ぎ継続率向上が期待できます(学生からも「教師の教え方が自分に合っていたら」「授業の進度が速すぎなければ」続けたいとの声ありjapanese-edu.org.hk)。質の高いコンテンツ提供と柔軟な授業運営への取り組みは、継続率の改善につながると報告されていますcajle.ca。
- 学習意欲の喚起と維持: 学習者の興味・関心を引く工夫を凝らし、内発的動機づけを高めます。具体的にはマンガやゲーム、マルチメディア教材、プロジェクト型学習などを取り入れて授業を楽しめるようにし、文化的トピックへの興味も喚起することが有効ですcajle.ca。また明確な学習目標の設定を支援し、小テストや課題で達成感を積み重ねさせることで成功体験を提供すれば、学習継続の意欲向上に効果があるとされていますjapanese-edu.org.hk。
- 教員の教授アプローチ改善: 教員研修や授業観察を通じて、学生主体の双方向型授業や分かりやすい説明、きめ細かなフィードバックの実践を促します。教師が学習支援者として学生の不安を軽減し自己効力感を高める関わりを持つことが重要ですjapanese-edu.org.hk。学生側も「教師の教え方が自分に合っていたら履修を続ける」と述べていることからjapanese-edu.org.hk、教授法の改善や教員と学生の信頼関係構築が継続率向上に寄与します。
- 柔軟な履修環境の整備: 他の科目との両立がしやすい時間割編成や履修形態の柔軟化(例えば夜間クラスやハイブリッド/オンライン授業の提供)を行います。時間割の競合を避け「別の授業と重ならないよう良い時間帯に」科目を開講する配慮は継続履修の可能性を高めると指摘されていますjapanese-edu.org.hk。事実、工学部生など忙しい学生でもオンライン併用のクラスであればスケジュールに組み込みやすく、履修継続に効果的だった例がありますcajle.ca。
- 学習コミュニティの形成・所属感の醸成: クラス内外で学生同士や日本人との交流機会を増やし、学習コミュニティへの帰属意識を高めます。例えば日本語会話テーブルやピア・ラーニンググループ、メンタープログラムの導入により「仲間」との関わりを促進すると、相互支援によって学習意欲が維持・向上しやすくなりますobirin.repo.nii.ac.jp。心理的要因へのサポート(言語不安の軽減や相談体制の整備)も不可欠であり、安心して学べる環境づくりが継続率向上に寄与しますfukutake.iii.u-tokyo.ac.jp。
- 履修継続へのインセンティブ付与: 学生が「続ければ得する」と感じられる制度設計も有効です。例えば日本語を副専攻として認定するプログラムの新設や、所定の科目修了者に修了証・資格を与える仕組みは、継続学習の明確な目標となり得ますcajle.ca。上級日本語科目の開講頻度を増やし履修機会を用意することも重要です。実際、上位クラスの不足は継続意欲を削ぐ要因と報告されているためjapanese-edu.org.hk、学習者が中級・上級へ進める道筋を示すことで履修満足度と継続率の向上が期待できます。
Sources:
【9】 王敏東 (2018)「日本語の学習を継続しない理由についての一考察―台湾の非日本語学科の大学生の場合―」『日本学刊』第21号, pp.36-47japanese-edu.org.hkjapanese-edu.org.hk
【14】 Langton, N. (2018) “Retention of learners in beginning Japanese language classes: crisis and opportunities.” CAJLE Annual Conference Proceedings 2018, pp.147-153cajle.cacajle.ca
【30】 Matsumoto, M. (2009) “Persistence in Japanese language study and learners’ cultural/linguistic backgrounds.” Australian Review of Applied Linguistics, 32(2), pp.10.1-10.18growkudos.comgrowkudos.com
【31】 岩本惇子 (2015)「外国語学習者の学習意欲に影響を与える要因はどのように作用するのか」『言語教育研究』第6号, pp.9-27obirin.repo.nii.ac.jp
【34】 林怡廷 (2016)「外国語学習の継続を支援する研究 (研究計画)」東京大学山内研究室ブログ記事fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp